🎃 宇治拾遺物語について
2022/07/30
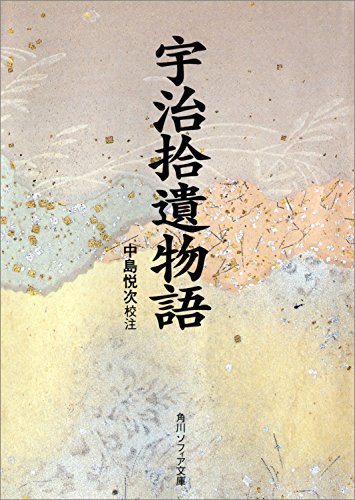 芥川龍之介は説話を題材にした短編で有名ですが、「宇治拾遺物語」に取材したものも結構あります(「今昔」と重なるもの)。
「地獄変」「鼻」「芋粥」などがそうです。
取材したとはいえ、芥川の作品は原典の単純な翻案といったレベルではなく、換骨奪胎し、いわゆる本歌取りレベルの別作品になっています。
「地獄変」はただ残酷な仏絵師の話を芸術至上主義者の悲哀という近代的なテーマにしていますし、「鼻」も単なる奇譚を傍観者の利己主義という視点からとらえています。
描写は「羅生門」の時代からそうですが、説話の語り口は皆無で、理知的でブッキッシュな近代人の文体になっています。
夏目漱石が激賞したというのも、作品が芥川の個性を明確に印したものになっていたからでしょう。
芥川龍之介は説話を題材にした短編で有名ですが、「宇治拾遺物語」に取材したものも結構あります(「今昔」と重なるもの)。
「地獄変」「鼻」「芋粥」などがそうです。
取材したとはいえ、芥川の作品は原典の単純な翻案といったレベルではなく、換骨奪胎し、いわゆる本歌取りレベルの別作品になっています。
「地獄変」はただ残酷な仏絵師の話を芸術至上主義者の悲哀という近代的なテーマにしていますし、「鼻」も単なる奇譚を傍観者の利己主義という視点からとらえています。
描写は「羅生門」の時代からそうですが、説話の語り口は皆無で、理知的でブッキッシュな近代人の文体になっています。
夏目漱石が激賞したというのも、作品が芥川の個性を明確に印したものになっていたからでしょう。
「宇治拾遺」には「こぶとりじいさん」「雀の恩返し」など、一般に日本昔話とされる作品の原話もあります。 それ以外では「伴大納言応天門を焼く事」や「秦兼久通俊卿の許に向ひて悪口の事」など、日本史や文学史の実際の事件を取り上げたものもあります。
結構よく出るのが鬼の話で、「こぶとりじいさん」以外に「修行者百鬼夜行にあふ事」「一条桟敷屋鬼の事」などがあります。 「百鬼夜行」では修行者が寺で夜を過ごしていたところ、鬼たちがやってきたので、不動の咒を唱えていたところ、不動尊がいらっしゃるといわれて外へ出され、朝になると原っぱのまっただ中にいたということになっています。
芥川は日本の昔話で、世俗の部を主に取り上げたのですが、実際のところ、上にあるように仏教がらみの話が多いわけです。 なぜ近代日本文学は仏教譚をタブー視するのでしょう。 キリスト教についていえばドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」は第一級の作品の扱いを受けていますし、アンデルセンのメルヘンには全てどこか宗教色があります。 近代科学の原点となったというデカルトの「方法序説」ですら合理主義の結論が神の証明ということになっています。
私見ですが、日本人は欧米文化にあこがれたあまり、伝統的な日本文化、中でも仏教というものに、何か非合理性と恥ずかしさを感じ、これを無意識に隠そうとしているのではないかと思います。 実際、「宇治拾遺」でも仏教がらみの面白い話は「増賀上人三条の宮に参り振舞の事」「慈恵僧正受戒の日延引の事」「提婆菩薩龍樹菩薩の許に参る事」「猟師仏を射る事」「道命和泉式部の許に於て読経し五条の道祖神聴聞の事」など数多くあります。 このうち、後の2話は坊さんの愚かさを笑うものですが、前の3話は純粋に僧侶の力を賛嘆するお話です。 中世日本は仏教を中心に回っていたことは間違いありません。
「晴明蔵人少将封ずる事」「晴明蛙を殺す事」に見られる陰陽師・安倍晴明のお話は現代日本のライトノベル系のファンタジーにはよく取り上げられるようです。 しかし、陰陽道は、仏教の加持祈祷の補完勢力でしかなかったはずで、平安貴族にとって、何といっても中心的なよりどころは仏教でした。 説話を取り上げて、仏教を無視するというのはこのように、ちょっとヘンですね。 これについては、また書きたいと思います。
※冒頭の写真は宇治拾遺物語 (角川ソフィア文庫)の表紙です。
| ツィート |  |
🕍 同ジャンル最新記事(-5件)
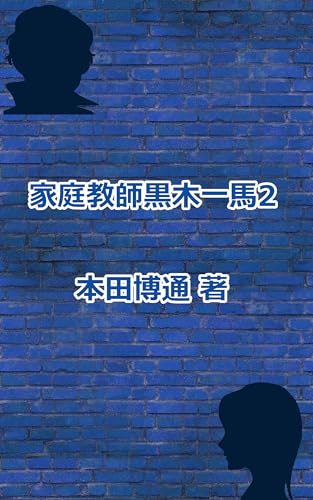 | 📕 家庭教師黒木一馬2出版(2024/04/07) 『家庭教師黒木一馬1』の続編です。現在のところ電子書籍のみですが、もう少ししたらペーパーバックも入手できます。以下、その紹介です。... |
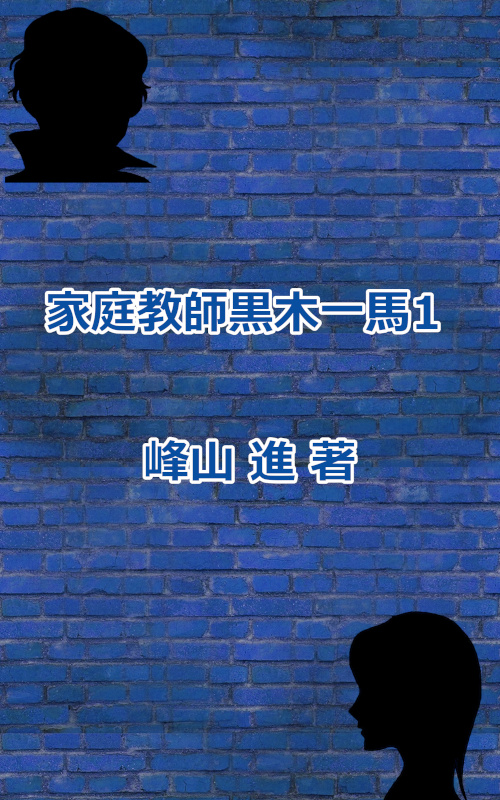 | 📔 家庭教師黒木一馬1出版(2024/01/13) ... |
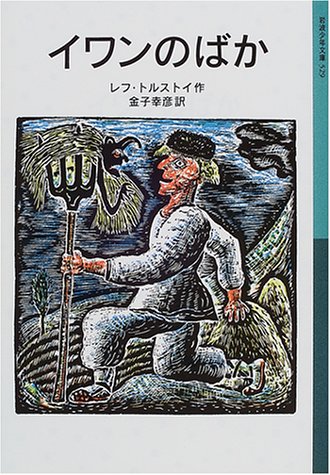 | 🤴 イワンのばか(2023/12/18) ... |
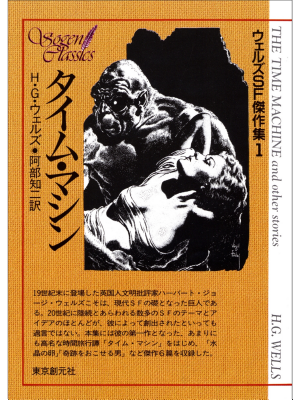 | 👾 H.G.ウェルズについて(2022/07/31) なぜだかウェルズには惹かれるものを感じます。子供の頃は夢いっぱいのヴェルヌのSFの方に惹かれていましたが、最近はどうもヴェルヌは食傷気味です... |
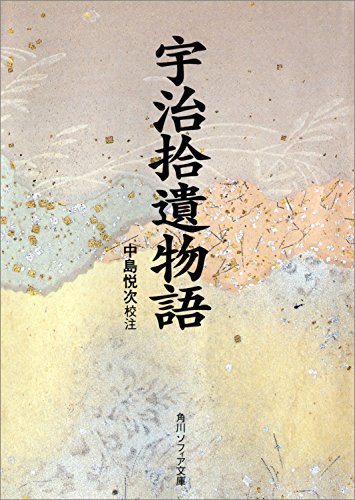 | 🎃 宇治拾遺物語について(2022/07/30) 芥川龍之介は説話を題材にした短編で有名ですが、「宇治拾遺物語」に取材したものも結構あります(「今昔」と重なるもの)... |